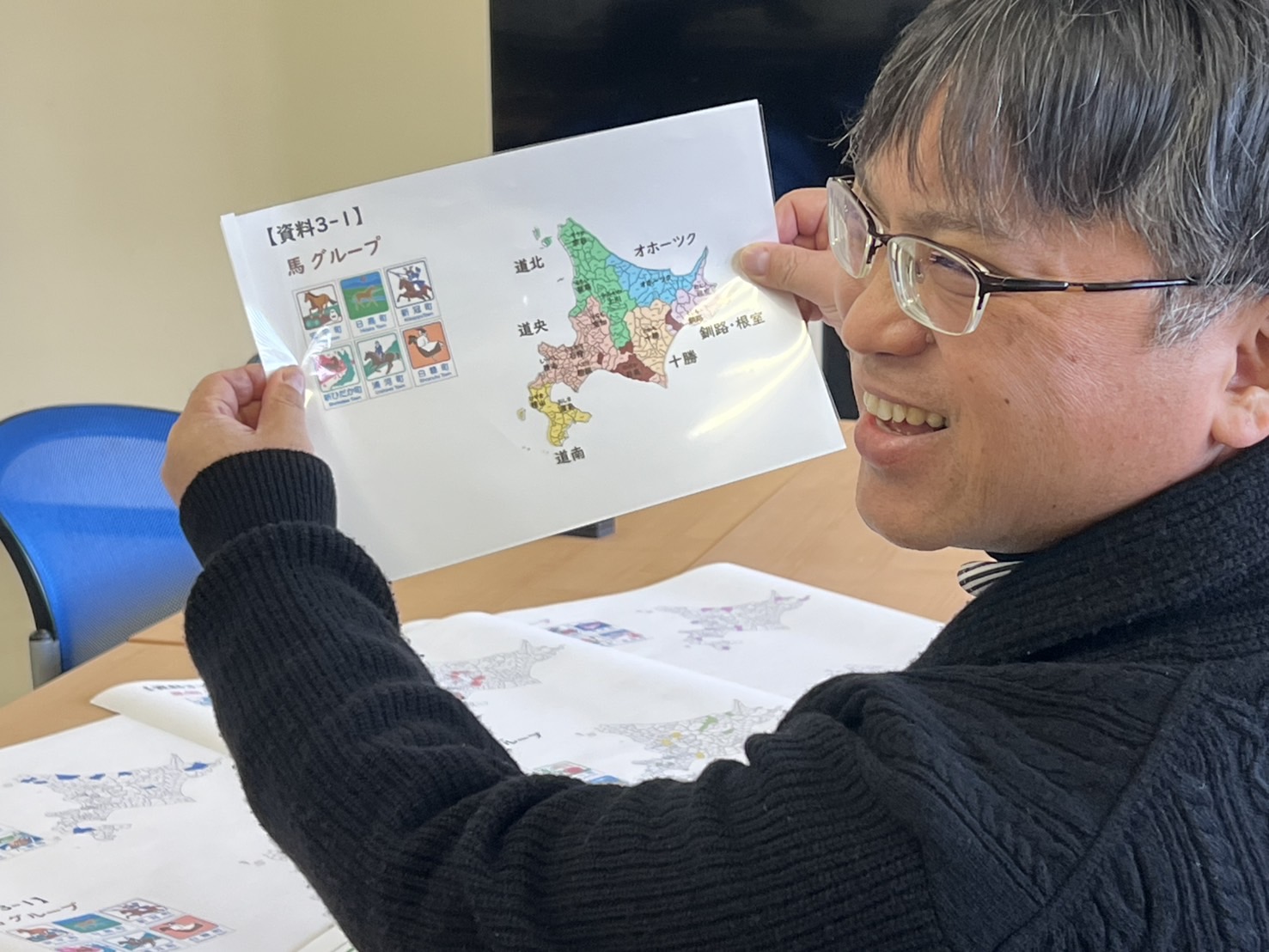南浦 涼介(広島大学)
授業当日
さて,いよいよ第2回の授業日がやってきました。
今回の実際の授業の様子は,以下からご覧いただければと思います。(YOUTUBE動画は,現在公開準備中)
もしも第1回の授業の様子と比べてみたいものずきな方がいらっしゃったら,ぜひ以下のリンク先の動画と比べてみてください。
今回,第1回と第2回のT1同士(つまり僕と草原先生)のかかわりに違いがあるとしたら,1回目はビギナーの僕に対して,それを草原先生が尊重する形で意を汲んで動くという形を取っている。今回の2回目は,少し役割を分けてみようということで,南浦が進行(司会や発問),草原が動き回って子どもを当てたり,ZOOMの向こう側の学校を当てたりする役割をすることになった。(なお,第3回目はさらに変えて「お互い好きなように動こう」となっている)
前回,僕は結構緊張もあって早口になってしまっていたのだけれど,今回はかなり落ち着いて,言葉を切ったり,溜めを入れて問うたりすることができていたかなと思っている。
「マイノリティ性」に光を当てることの機微
今回は試みとして,東広島市だけではなく,広島市の基町小学校が入ったことはとても大きい。とくに,後半の「聞き上手になろう」のところで出てきた,基町小学校の校内放送と,その放送を実際におこなった子どもに,授業の中でそのときの気持ちを聞くということや,それについてみんなで考えるということは,こちらもかなり気をつかう内容だった。
あらかじめ先生方とそのことについてうちあわせをして,本人にもそういうことを聞くからねと伝えていたりして置いた中で実施をした。こうしたみんながいる場の中で,何も前提やフォローをしないままにマイノリティ性に光を当てることは,ただただ少数者であることを周りが見るだけになってしまうことにもつながりかねず,十分に気をつける必要があるからだ。
ただ,今回は学校として「大丈夫」ということを言われていた。それは何よりも,ここではそうした外国性や多文化性は「あたりまえ」のことだから,ということだった。まただからこそ,なによりも今日ここで光が当たることは,彼にとっても大きな自信になるはずだという先生方の確信もあってできたことだった。
授業の中で子どもたちが得た勇気
各学校の教室には,スタッフとしてカメラや機器をあつかう学生たちが派遣されている。学生たちは当日,LINEをつかって状況をつたえあっているのだけれど,基町小に行っていたスタッフの川本さんによれば,新幹線の車掌さんが英語を頑張って学んでいるシーンをみて,放送をしていた子どもが「そうだよ,俺だってがんばっているんだ!」と周りの子どもたちに言っていたりしていたそうだ。とてもうれしいエピソードだった。
この授業の中で起きたことは,日本語も頑張って学んでいる子どもたちも含めて,さまざまな力につながったのではないかと思っている。放送をしている子どもの様子を,別の小学校にいる外国につながる子どもが,食い入るように見ていたのも印象的だった。
今回の授業で得たこと
今回の授業を通して,僕はこの広域交流型オンライン学習の「多文化共生」はどのようにあると良いのかが少し見えたように思っている。
社会科の授業の場合は,東広島市の中にある「地域差」に着目することで,同じ地域の中にある違いを交流したり,違いから問いを展開させていくことが重要になる。一方で,「多文化共生」の場合はどうだろうか。もちろん「地域差」を考えることも1つなのだけれども,東広島市は広島県の中でも抜きん出で多文化的地域になっている。一方でもともとは農村地域だったこともあり,そうした外国人との共生の歴史自体は長くない。
だからこそ,「域内の差」ではなく,東広島市全体として,「域外との差」に着目しながら他の地域に学ぶという点が重要になるのかもしれない。基町小学校がそうだったように,そこではあたりまえになっていることが,実はあたりまえではなく,価値があることだと気づくこともまた「域外との差」の中で見えてくる。こうした「域外交流」はとても重要で,それによって生まれるそれぞれの「ゆらぎ」こそが,多文化共生への目につながっていくのではないかと思った。
外に伝え,外に学び,内を捉え,未来を考える──こうした学びが「広域交流型オンライン学習:多文化共生編」のよさなのかもしれない。
2023年の春に広島大学にやってきました。「先生」の仕事は23年目,大学の先生の仕事は14年目,広島大学の先生の仕事は2年目の古米のような新米です。授業や多文化共生の教育の仕事が大好きですが,ラーメンも好きです(最近控え中)。
-
アクティビティ
-
アクティビティ
-
アクティビティ