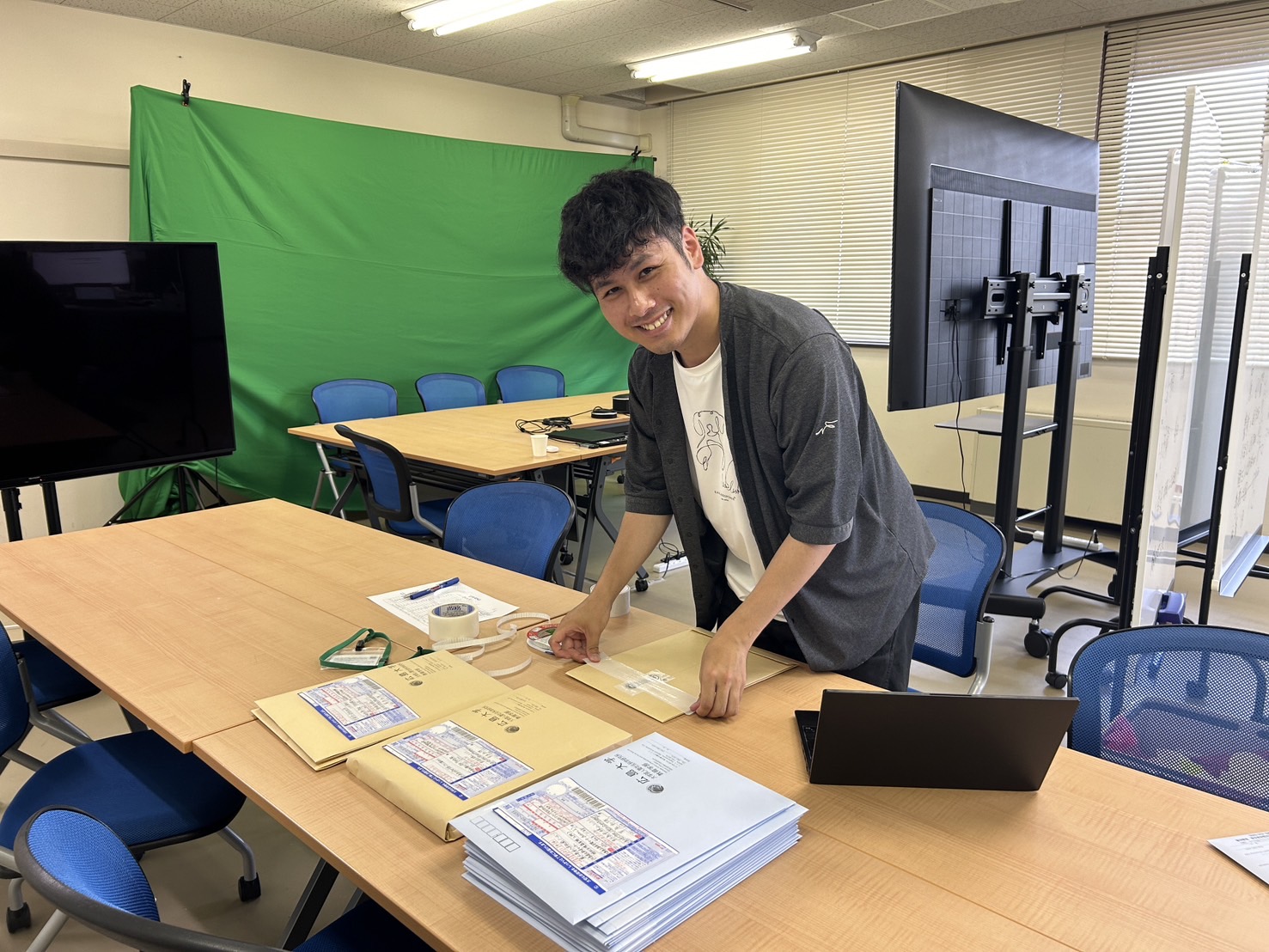南浦 涼介(広島大学)
1.9月某日,基町小学校前にて
さて,2024年9月某日,まだ太陽がギラギラと照りつける残暑の広島市。僕は基町小学校に来た。前にも触れたように院生時代から何度も訪れているので,自分としては慣れた学校なのだけれども,いつも緊張します。緊張の在処は,院生時代にここで「修業」したということがあるので,いつも修業場を訪れていたあの頃を勝手に僕が思い出すのと,もう一つは,学校は子どもたちも先生方も時の中で入れ替わり,新陳代謝していくので,その点で別に僕は常連でもなんでもないからだ。だからいつも「初めましてで関係をつくりあげていく」という緊張があるのだと思う。
今回はまして,「東広島市で行っている取り組みの授業実践に一緒に参加しませんか? そしてその中でこの学校でやっていることを紹介いただけませんか?」という内容で,「そもそもこの事業は……」からの説明が必要となるので難易度が高いなあ……と思いながら学校の前に立っていた。
ただ,現校長先生の森貞先生とは実は初めてお会いしたわけではない。この1ヶ月前に,別の用事で以前ここに勤めていらっしゃった校長先生(元校長先生)と一緒にお伺いする縁があり,その際にご挨拶をさせていただいた。ということで2回目のご挨拶だなあと思って校長室の扉を叩いて中に入らせていただくと,なんと奇しくも,現校長の森貞先生だけでなく,たまたま別件で来られていた先日一緒に訪問をさせていただいた元校長先生もいらっしゃって,「え,何々? どういう計画の話?」と水を上手に向けられ,なんとも和気あいあいとした空気となった。ありがたい……!!
そうしたことで,仮版のチラシをもって事業の内容と授業の内容を説明し,「ここで基町小学校の放送委員のシーンを見て,それについてみんなで考えさせていただけないかと思うんです……!」とお願いをした。どうかなあ,大丈夫かなと思っていたのですが,森貞校長先生からは開口一番「ぜひ!」だった。ホッとした。あまりにも即決だったので,「え,本当にいいんですか……?」と聞いてしまったくらいだ。「もちろん担任の先生も確認を取りますけれど,私の中では『あの学年!』ともう目星があるんです」とニコニコ顔。
こうした形で,ひとまず,基町小学校の参加が動くことになった。
2.基町小学校の参加をふまえて,チラシをつくる
明けて,チラシ検討の第2回目,今度は「基町小の参加」を前提とした授業チラシになっていった。チラシをつくるというのは,実は結構塩梅が難しい。学校の先生が見て,「お,なんだか面白そう」と思える,つまり「風景がうかぶ」程度には展開を具体化しないといけないのだけれど,チラシという制約もある。学校の参加によって変わるとこも具体的にはある。でも,そうした中で「基町小学校が参加します」というのは具体化しやすく,また,学校にとっては「あ,多文化共生の取り組みで聞いたことがある学校だ!」とイメージしやすくもなり,このあとの作業がとても動かしやすいところとなったのだった。
「デジタル・シティズンシップ・シティ:公共的対話のための学校」プロジェクトメンバーである三井・川本・宇ノ木・神田が更新しています! ぜひ、本記事を読んだ感想や疑問・コメントをお寄せください!
-
アクティビティ
-
アクティビティ
-
アクティビティ