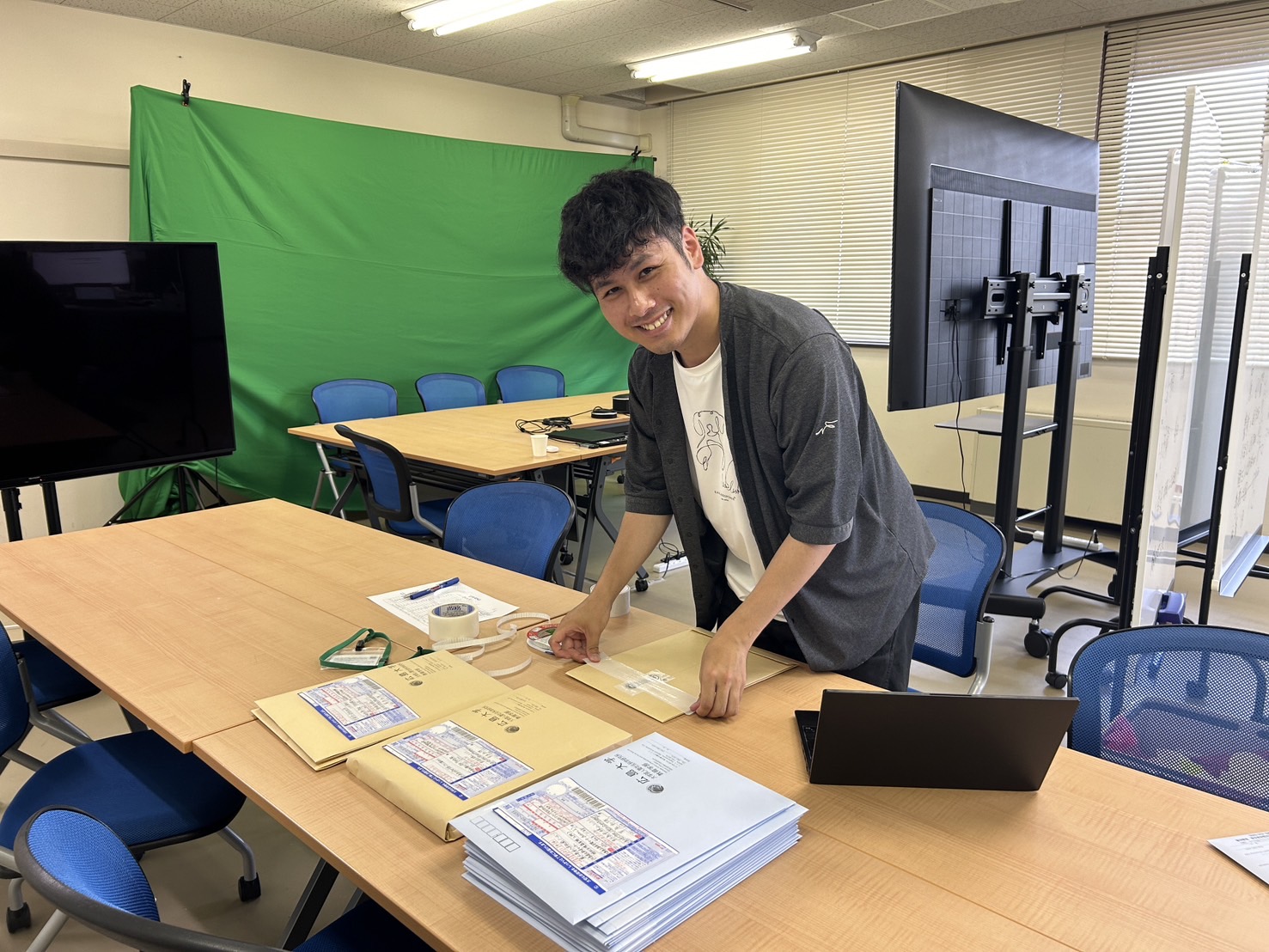南浦 涼介(広島大学)
T3(学生サポーター/学級支援者)の視点から
「多言語お知らせ」をめぐって授業づくりを記しているのですが,今回は「番外」的な扱いになるかもしれないけれど,つい先週(2025年6月18日)に「T3」として参加してきたことを書いておきたい。
「T3」というのは「3番目の教師」で,よく学校でTeam Teaching(ティーム・ティーチング:つまり複数の教員で行う授業)を行うときには,こうやって「T1:主として授業を動かす教師」「T2:補助や支えとして動く教師」と緩やかに棲み分けながら授業を行う。もっとも主と副は関係性によるところが大きく,場合によっては「どちらも主!」みたいな授業もあるので,あくまで「番号付け」くらいかもしれない。
広域交流型オンライン学習では「T1」をオンラインを回す司会進行役としての教員(南浦や草原先生),「T2」を各学級の担任の先生としている。
ちなみにこれまで書いてきたように,ここには主副の関係は本来なくて,正直学級の動かしは学級の担任の先生にお任せするのがいちばんよく,T1の大学の教員はあくまで「全体の回し」に徹することだと思う。
さらにそこに「T3」がいる。T3は学生スタッフたちだ。各学校のクラスで,カメラや音声管理,マイクの管理,突発的な事態に対応したり,子どもたちを前に立たせたり,参観に来た人への対応をしたり,いろいろなことをする。
今回,授業をT1以外の視点から見ることで,自分の実践感覚を磨く意味あいもあって,学生と一緒に社会科の草原先生の授業(古墳)を「T3」として学生スタッフの1人となってかかわった。これまでの奮闘記では,この「学生スタッフの視点」があまり描かれていない。今回,番外編を発出することにしたキッカケは,「多言語お知らせ」の授業実施を見る上でも,この「学生がいる」という点はとても重要で,そこを見るためにもいちど「学生の動き」を描くことが重要だと思ったからだ。
T3の素人としてはじまった
正直,T3に関して言えば僕は素人で,ぜんぜんしらない。同じ学校の配属に,南浦研究室から参加している4年生の学生がいるのだけれど,彼女のほうがだんぜん先輩である。先輩だし頼っていればまあ半人前でもなんとかなるか,と鷹揚に最初構えていたら,2組の担当が必要だという話になり,「じゃあ,南浦先生は2組を担当してください。私は3組でいくので」とキビキビと「先輩」に指示され,あっという間に一人前ゾーンに放り出されてしまった……。
とはいえ,集音マイクの設定,AIアプリの起動などの準備はT3になっていなければ実は見えにくい。ホスト校にいると,色々な指示があるけれども,その他の学校の場合は,教室と画面の向こうをつなぐのは学生スタッフだ。この点はT1をしていると実は実感がしっかりと及んでいないのだなと改めて感じる。
学校について,校長先生に挨拶をし,撮影などの確認をし,2時間目と3時間目の間の「大休憩」(と広島では呼ぶ。極めて珍しい言い方で,いわゆる「中休み(関東に多い)」「長休み」「20分休み(兵庫の阪神地域に多い。僕はこれだった)」というやつだ)の間のごくわずかな時間で,ZOOM接続,マイク確認,カメラ確認,先生との打ち合わせ,AIアプリと非常に慌ただしい。ちょっとでも不具合が起きると焦る。
実際僕の場合,マイクがうまく聞こえないという事態が起きて,非常に焦った。途中からは教室に帰ってきた子どもたちが興奮しているのもあって,話しかけてくる中を対応しながら機器を接続していく。
T2とT3の「呼吸」が生まれてくる
ギリギリでなんとか設営ができると,もう授業がはじまる。「みなさんおはようございます」といつもの草原先生のはじまりの声が聞こえだす。ただ,「画面の向こう」にいるというのは,ホスト校にいるとなかなか味わえない感覚だ。Eテレの授業を見ているような「遠さ」「客観さ」を感じる。だからこそこの授業は,それを「使いながら」担任の先生がどう動くかと言うことがとても重要になる。僕が担当していたクラスの先生は実は,15年ほど前に同じ小学校で働いていた元同僚の先生だったのだけれど,さすがの授業力。テレビの向こうの草原先生の司会を巧みに受けながらも,教室の子どもたちに「じゃあ,こっちも考えてみよう!」と促し,問いを確認しながら授業を進めていく。ホスト校だと感じにくいのだけれど,やはりこの授業は圧倒的に「T2」という担任の先生が「主」なのである。
「それぞれの学級の意見を聞いてみよう!」となると,ZOOMの「挙手」の競争になる。「こちら側」にいると,他の学校に伝えるチャンスというのは実は極めて少ない。参加校が増えるほど,「自分たちの学級の意見」を伝える機会自体は減ってしまうのだ。だから「たのむ,私たちを当ててくれ〜」という感じになるし,一方で当たったら「ギョギョギョ,あたっちゃった!」となってドギマギもしてしまう。(T3がZoomの「挙手」ボタンを押さないと当たりにくいのでメチャクチャ責任がかかる笑)
だからこそ,「相手の意見を聞く」も重要になる。ちなみにクラスの先生はさすがの力量。隣のクラスが発表したら,「ハイ,みんな3組に向かって拍手〜」と促し,空間を隔てた向こうの世界に拍手を送り,子どもたちが「つながっている」という意識を持続させようとしている。
また,「ZOOMを介して意見を交換」だけではない交流活動も重要だと改めて感じた。ブレイクアウトルームの活用で小規模で話し合う,スライドをつくりながら自分たちの作品を見せ合うというのは,参加校にとって「つながり」を感じる重要な機会だ。
通常の授業でも先生の視点だと「色々な子どもの声を重ねている」と見えても,子どもの立場から見ると,「なかなか当たらない!」と言う感覚になるのと同じかもしれない。
LINEでそれぞれの教室の様子を報告しあいながら,教室の子どもたちの様子を写真に収め,機器の管理をするのはいわゆる「ワンオペ」的に複数のタスクを一度にこなしていく複雑さを持っている。一方で,だんだん慣れてくると,担任の先生と「T2とT3のあうんの呼吸」みたいなものが生まれてきて,先生の呼吸を見ながら,ZOOMの画面の「ここ見てみて!」「よし! 次は当たるぞ! 気持ちの準備だ!」などと子どもにT3として声をかける余裕もでてくる。
これが出てくると,画面の向こうが不思議と「Eテレ」ではなく,「実際にいる画面の向こうの子どもたちとのつながり」を感じる空気が生まれてくる。媒介となる人の存在はだからとても重要だ。むしろその点では「T3が空間をつないでいる。授業を動かしている」面がかなりある。ゆえにぼくらは「T3」なのだ。そういうことなんだなと再発見した。
いろんな「センセイ」によって成り立つ授業
この授業はこのように,いろいろな「先生」の存在でできている。「チャンネル2」として,同時に不登校支援の場にも授業を開設(解説)・配信しており,そこではさらに別の役割として先生をして,つないでいるスタッフがいる。古墳公園から中継をしているスタッフもいる。それぞれが場の主体となって動いていることで,躍動感や力動が生まれている。授業って,「授業者」と「学び手」だけでできているんじゃないんだよな。
なにより,個人的によかったのは,学生と同じスタッフとして動くことで,一緒の目線になり,一緒に働くという感覚が増したことだ。学校に向かう道中の話,タスクと作業を共有するからこそうまれる一体感。そうした場に主体性を持って僕を放り込んでくれたゼミの「先輩」に心から感謝だ。
2023年の春に広島大学にやってきました。「先生」の仕事は23年目,大学の先生の仕事は14年目,広島大学の先生の仕事は2年目の古米のような新米です。授業や多文化共生の教育の仕事が大好きですが,ラーメンも好きです(最近控え中)。
-
アクティビティ
-
アクティビティ
-
アクティビティ