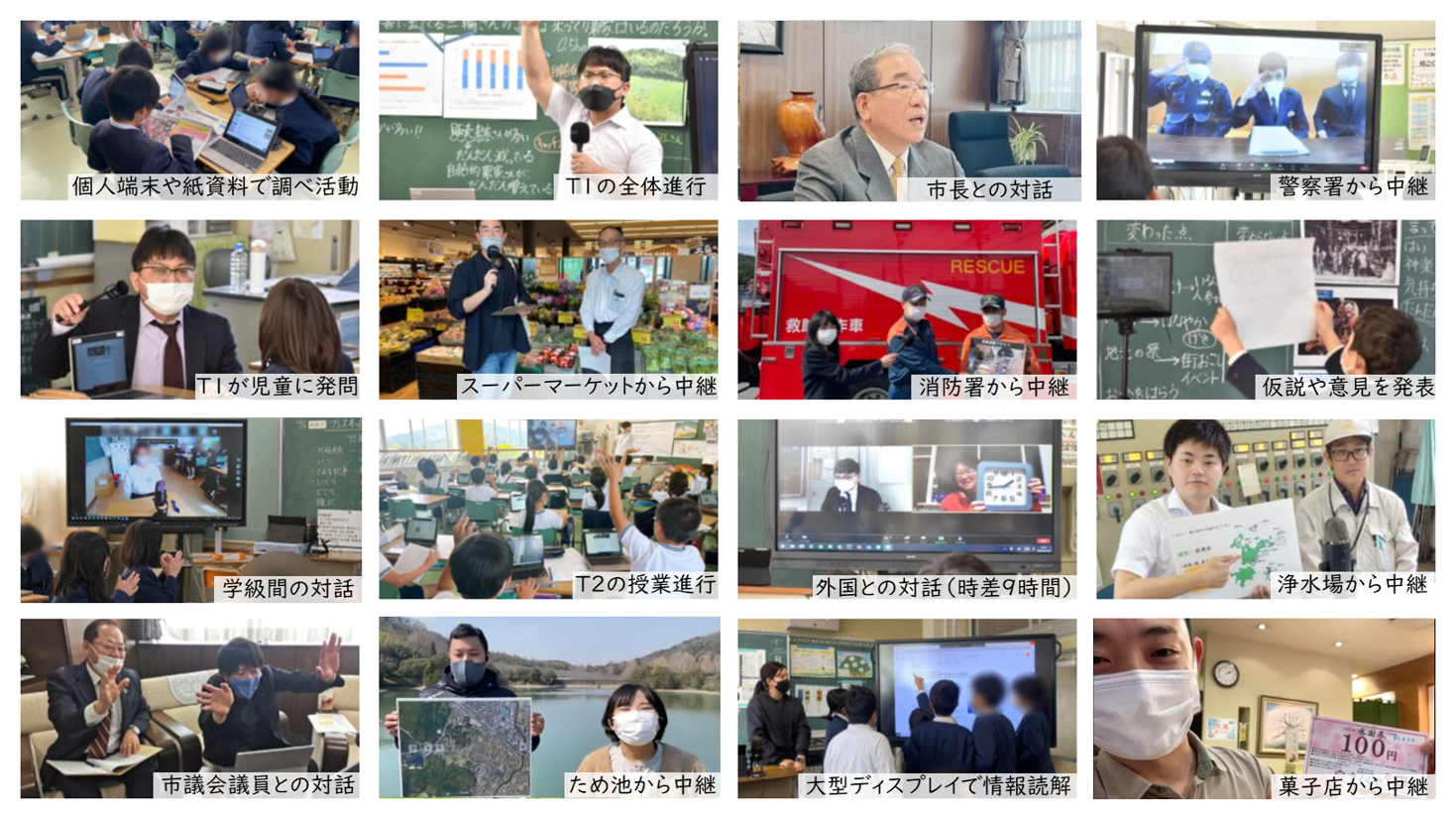南浦 涼介(広島大学)
1.第2弾のはじまり
しばらく開けてしまった,メイキングオブオンライン授業の第2ターンのはじまりです!
実はすでにかなり時間を空けてしまったこの奮闘記録,ときどき「どんなふうに授業をつくっているのか」ということを聞かれることがあって,そのときに,こういう「メイキング」の意味はあるのだよなと改めて思います。
さて,2024年の秋にさしかかった頃,「第2弾」の多文化共生編の授業チラシをつくる会議がはじまりました。もともとの計画であったように,第2弾のテーマは「外国の言葉が上手ってどういうこと?」でした。このテーマになったのは,前にも述べたように,「教科」ではないこの多文化共生編の授業は,学校の先生たちにとって「どこで行なうか」が見出しにくいところがあるからです。本来「カリキュラム・マネジメント」という自律性に帯びたはずのマネジメントが「年間で決まっているから」という名の下に,ガチガチで柔軟性がない,自分たちの何にかかわるのかを,自分たちで見出すことができないというのは本当に「カリキュラム・マネジメント」だといえるのかという問題は改めて問うべきだと思います。が,経験のないものに対するかかわりにくさは致し方ないところでもあり,その点で今回のテーマは「外国語」とのかかわりも見出しやすいところがありました。
2.「外国のことばを上手に話す」を考える3つのアイデア
「外国の言葉が上手ってどういうことか」ということを考えてもらうのに,僕の中で3つの事例になりそうなアイデアを持っていました。
1つめは,「新幹線の車掌さんの英語放送」です。最近,JRの新幹線では,以前はネイティブの英語の人による自動放送だったものが,次第に車掌さんの肉声の英語による放送に変わってきました。車掌さんたちは別に英語の専門家でもない。そのため多くの場合「たどたどしい」わけですが,「流暢な自動放送」から「たどたどしい肉声放送」に変わってきたことの背景には,「上手さ」の捉え方を考えるきっかけがあるだろう,と思ったことです。
2つめは,これは僕たち自身がそうだと思うのですが,「外国語ってノンネイティブ同士で話すときが一番気楽だ」ということです。実はかえって「ネイティブの人と話すとき」が一番緊張する。これってなぜだろうかということを考えることは,やっぱり,「上手さ」を考えるきっかけになるだろうと思いました。
最後の3つめは,広島市内にある外国にルーツを持つ子どもたちが多い小学校(後でもでてきますが,基町小学校といいます)で,長年されている取り組みで,外国から来たばかりの子どもたちも「放送委員」の仕事をするという取り組みをしていることです。僕は自分自身の研究の関係で長年この小学校とかかわってきたのですが(学校自体の取り組みの詳細は,南浦・二宮,印刷中),この取り組み自体にも「上手さ」を考えるきっかけがあるだろうと思ったのです。
3.基町小学校も一緒にどうですか?
これらをひっさげて会議に臨みました。さて,前回の第1弾のように,七転八倒七転び八起きのごとくリテイクが続くかと思っていたのですが(いや,続いたのですが),結構最初から受けがよく,さらに「これなら基町小学校も『教材』ではなくて,参加校として入ってもらったらどうか」という話がでるまでになりました。「南浦さん。その可能性はありますか?」と草原先生。「聞いてみましょう!」ということで,今回第2弾の大きなキーになる,基町小学校に改めておたずねに上がることになりました。
2023年の春に広島大学にやってきました。「先生」の仕事は23年目,大学の先生の仕事は14年目,広島大学の先生の仕事は2年目の古米のような新米です。授業や多文化共生の教育の仕事が大好きですが,ラーメンも好きです(最近控え中)。
-
アクティビティ
-
アクティビティ
-
アクティビティ