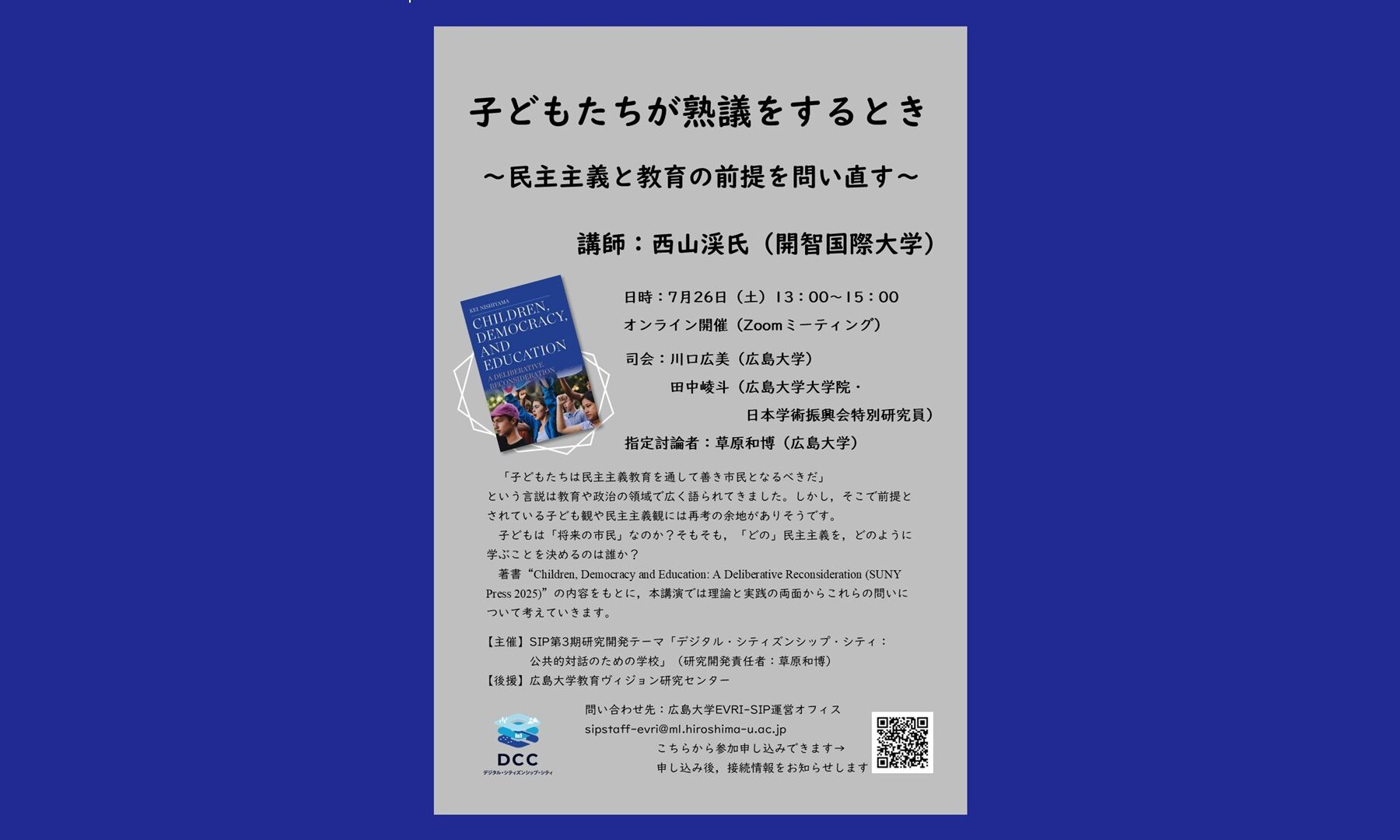南浦 涼介(広島大学)
授業をする先生方(T2)との打ち合わせ
さて,授業当日の1週間前。それぞれの学校から申し込みのあった学校・教室の先生たちとの打ち合わせの日になった。どこかでも触れたけれど,この僕のやっている「多文化共生」編は教科の授業ではないため,実は最も苦労するところがこの「参加校」募集だ。実際,第1弾のときの参加校は2校だった。ところが今回の第2弾は,なんと4校とスクールSが参加し,3年生から5年生まで200名近くの子どもたちが参加する大規模なものになった。
今回の授業のタイトルが「外国語を上手に話すってどういうこと?」という名前になったことと,基町小学校という「外国につながる子どもたちの多い学校」が参加するということが「外国語」の学習との関連づけを得やすいと判断する学校があったり,また前回のやさしい日本語の授業から続けて参加された学校もあったりした。正直,学校が参加してくれなかったらどうなるのかと思っていたので,ホッとした。
前回の打ち合わせのときは,僕自身が実は緊張もしていて,指導案の説明を半分くらいしか説明できていない状態でミーティングの終了時間が来てしまったのだ。オンラインで会場設定も含めて行うことや,それぞれの学校のタイミングもあって,ここが結構むつかしい。
自分自身が2回目ということで,慣れってすごいなと思うのだけれども,今回はそうしたイレギュラーな中で,教育委員会の瀧本指導主事のリードもあって,指導案のコンセプトの説明も,先生たちとのやりとりもそれなりにうまくいったと思う。(実はこのときの外国語専科の先生はとっても元気な先生で,画面越しだけれどもとても僕が勇気を得た)
このときもう一人のT1の草原先生は実は所用でミーティングの場にはほとんど入ることができず,その点で指導案の説明も授業の説明も僕だったのだけれども,この点は心底ほっとしたところだ。
T2を引き受ける担任の先生の「機微」のすごみ
後日,今度はホスト校になる小学校に訪問した。授業の意図はすでに伝えてあり,教室をどう構成するか,電子黒板をどこに置くかなどをうちあわせていった。実際,学校の先生からしたら,普段自分が授業をしている教室に知らない先生が入ってきて,普段のペースをふまえながら,子どもたちの学習を任せるのはきっと心もとないだろうと想像できる。そうした中で,授業をある意味でT1を任せてくれるというのはなんという勇気だろうと思う。
実際,T2の先生は大変で,授業のペースを守りながら,子どもたちを見て,話し合いを動かしていく。これはまたT1とは違う機微が必要なところで,授業の進行を任せながら対話を自分のほうで動かしていく。ほんとうに汗をかく仕事だと思う。
この先生方との関わりの中で,この授業は進行していくのだと言うことを改めて思った。
そして,2回目の授業の本番がやってきた。
2023年の春に広島大学にやってきました。「先生」の仕事は23年目,大学の先生の仕事は14年目,広島大学の先生の仕事は2年目の古米のような新米です。授業や多文化共生の教育の仕事が大好きですが,ラーメンも好きです(最近控え中)。
-
アクティビティ
-
アクティビティ
-
アクティビティ