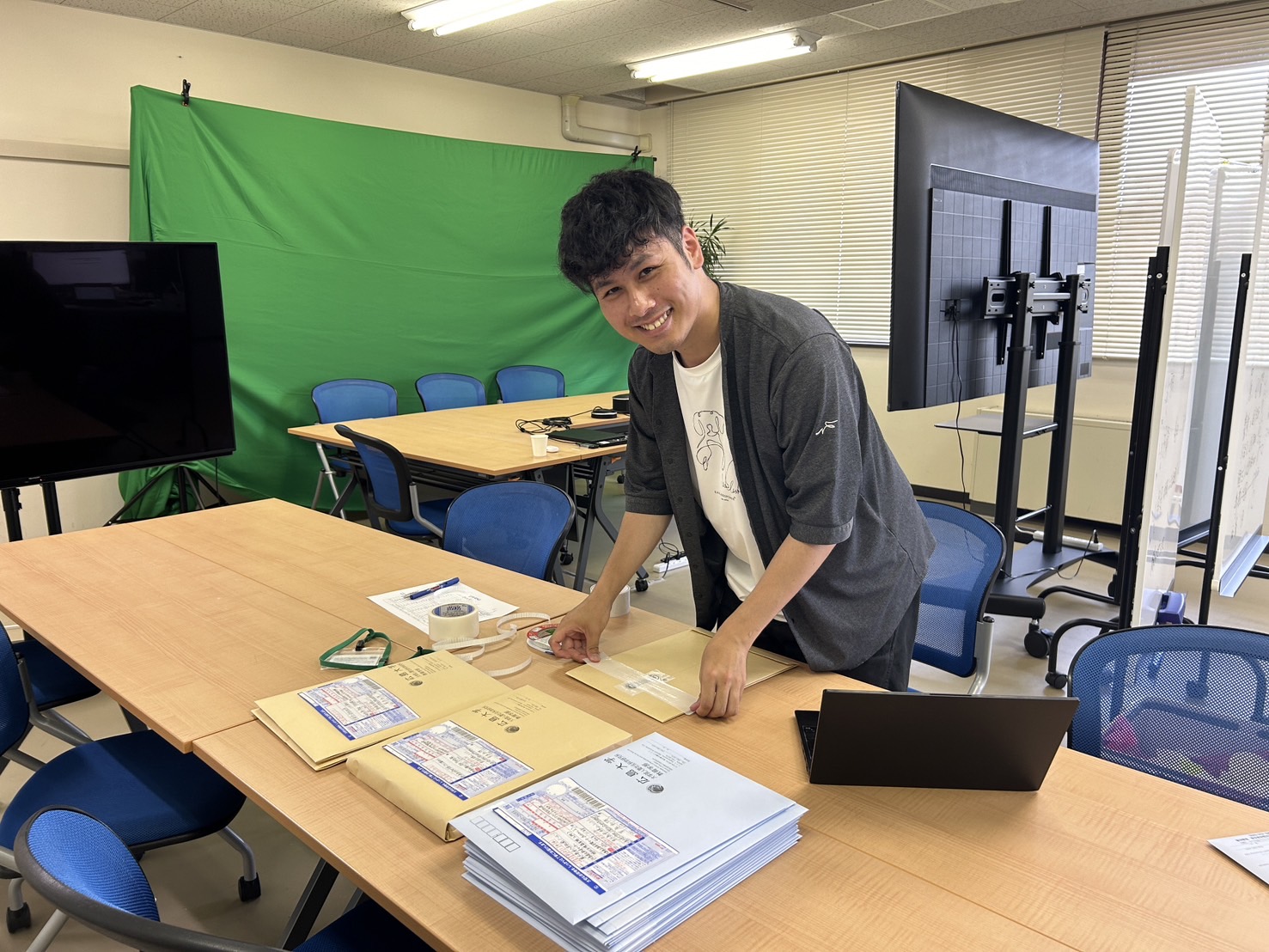南浦 涼介(広島大学)
あっというまに決まったチラシ第3弾
さて,前回からはじまった第3シーズン。多言語看板というネタを決めて,なんとあっというまにチラシ案の提出になりました。そして驚くべきことに,あまり修正事項がなく,「これでいきましょう」ということに。なんだかもう一人のT1の草原先生もにこやかです。「私の次の授業の所もこれでいこうかな」という始末(その後確かに,韓国の多言語看板を扱った授業が実際になされたので影響は本当にあったらしい)。
今回の授業の内容は大きく2つのテーマがある。
1つは,多言語看板は「多言語をたくさん載せたい」「でも制約がある」という中で「いくつ載せるか」ということに価値判断が分かれるところが教材になるという点。
もう1つは,多言語看板はなぜか世の中では「注意してほしいこと」「気をつけてほしいこと」という注意系看板に多いこと。(その1で見た横浜の看板もそうだったね)
この2点を考えることで,「公共性と効率性」をめぐって,色々な議論ができそうだと言うことである。こうした作りは,わりと社会科教育の観点にも近いものがある。その点で他のメンバーにも内容がイメージがしやすかったのかもしれないし,そもそも,僕の中にある社会科を専門にしていたアイデンティティがわりと授業づくりにも活かされていたのかもしれない。

子どもたちにとって身近な「多言語看板」をさがして
ただ,このときにはチラシ案はあくまで「アイデア」。子どもたちの身近なもので考えないとただのおもしろクイズになってしまいかねない。そのためには,自分たちの身近なところにある多言語看板である必要がある…しかもそれは「公共性の高いもの」でみんなのものであるということがないといけない。
まだ参加する学校も決まっていない中でこの「当事者感覚をたかめるもの」が何だろう…。ひとまずチラシの上では東広島市の子どもたちを想定して「のんバス」だったのだけれど,実際はのんバスは東広島市の中心部の西条町のそのまた一部でしか走っていない(ただ授業では登場することがあるから知ってはいるだろう)。また,そもそも「のんバス」には多言語表記があるだろうか。あるとしてこの授業の流れでは,バスの中に表記はあるけれど,ほとんどのものにはなくて,あったとしても1つだけ「立たないで」という注意系のものだけになっている必要がある。
本当に多言語表記はあるのか。またそれは注意系だけになっているか。(実際,息子と夏休みに乗ったときがあって,そのときはそうだった。それがこの授業のもとになっている)
実際に乗ってみなければということになった。果たして「のんバス」にそれはあるのだろうか? 時間をぬってまずは探索開始! である。

「のんバス」にそっと乗ってみた
そして乗ってみると──おお,あった! 夏の通り,「危険ですのでバスが停留所で完全に停車しドアが開くまで席を立ったり移動したりしないでください」のお知らせが「英語・中国語(大陸),中国語(台湾),韓国語」になっている。そして他には──ない! これだけだ。
よかった。ひとまず「多言語表記はある」「でも1つだけ」「注意系」だった。夏と変わっていなかった……(地域として考えればもっとあっていいとも思うけれど,教材的にはホッとした。矛盾だ)
ただし,今回はあくまで確かめに行っただけ。正式な取材をきちんと依頼する必要がある。そして「のんバス」だけでもないだろう。広島市の基町小学校の参加もあるわけで,そこの周辺にはあるかどうか,東広島市の他にはあるかどうか。このあたりも探っていく必要がある。次回,取材をたくさんしていきます!
2023年の春に広島大学にやってきました。「先生」の仕事は23年目,大学の先生の仕事は14年目,広島大学の先生の仕事は2年目の古米のような新米です。授業や多文化共生の教育の仕事が大好きですが,ラーメンも好きです(最近控え中)。
-
アクティビティ
-
アクティビティ
-
アクティビティ